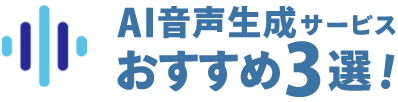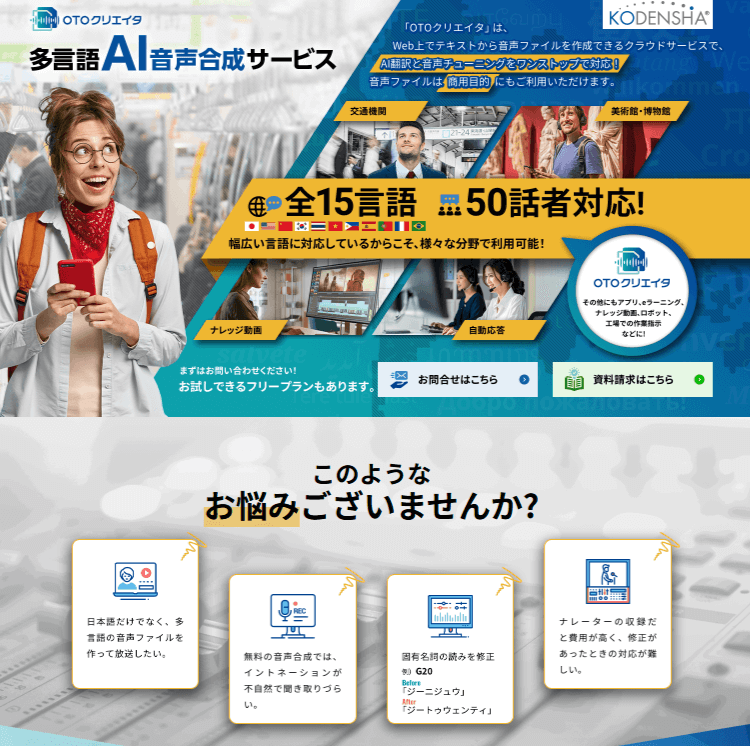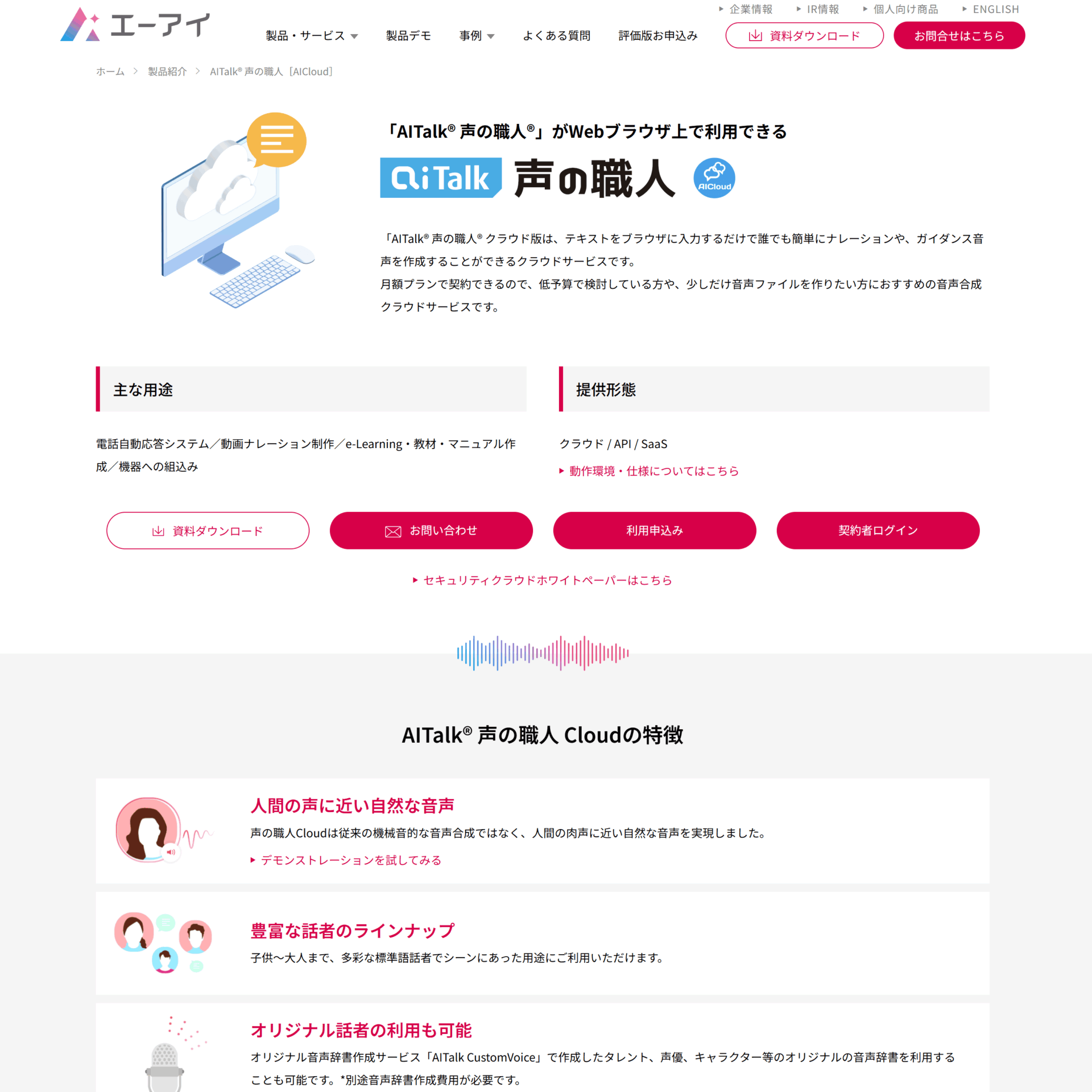近年、ナレーションやカスタマーサポートなど、多くの分野でAIで生成された音声が活用されています。一方で、学習段階での無断データ活用や、生成された音声が酷似していることで著作権侵害などに該当する懸念点もあります。この記事では、生成AIにおける、著作権の基本的なポイントや注意すべき点を解説するので、ぜひ参考にしてください。
AI開発と著作権をめぐるトラブル事例
近年進歩が著しい生成AI技術の中には、既存の音声データをもとに、新しい音声を生成できるサービスもあります。これらは、ナレーターなどの分野で幅広く活躍しています。
そのことはクリエイティブ業界に新たな可能性を広げる一方で、訓練データの収集や、利用に関する法的な課題も表面化しつつあります。つまり、これらのAIを開発する際に必要となるデータ収集は、慎重に行わなければなりません。
なぜなら、許可を取らずに収集した場合、著作権侵害とみなされる可能性があるためです。生成AIの技術進歩により、著作権侵害のリスクは世界中で見られ、多くの議論を呼んでいます。ここでは、生成AIによる著作権侵害トラブルの事例を数点紹介します。
AIイラスト投稿禁止
日本では2023年、イラストを取り扱うクリエイター支援サイトが、AI生成イラストの取り扱いを禁止しました。この決定の背景には、特定のクリエイターが不利益を被る可能性や、クリエイターの作品が無断で収集されることへの懸念があります。
画像生成AIによる写真集販売終了
日本のある出版社が電子版でのみ販売していた、画像生成AIを使用した写真集が販売終了しました。生成AIの論点・問題点についての検討が不十分であったためです。
この写真集には、実在する人物に対する類似性が見られるという意見があり、著作権が問題視されたことが引き金になり、販売終了にいたりました。
生成AI企業に対する訴訟
米国では、アーティストが画像生成AI企業を相手取った訴訟を起こしました。原告のアーティストは、AI企業が許可を得ずに作品を複製し、AIの訓練に使用したと主張しています。
また、米国の写真配信サービスも、数百万枚におよぶ画像が無断で利用されたとして、AI開発企業を提訴しました。さらに、米国の対話型AIサービス利用者が、AI開発においてインターネット上の個人情報を許可なく収集しているとしてサービス提供会社を訴えています。
要注意!著作権を侵害する可能性があるシーンとは
AI技術が進化する中で、その利用には多くのメリットがある一方、著作権侵害のリスクも多く指摘されています。とくに、AIの開発や利用が著作権法とどのように関係するかについては、しっかり理解する必要があるでしょう。
ここでは、AIを利用する際に、著作権へのリスクが高くなる場面について解説します。
AI生成物の利用段階のリスク
AIによって生成された作品の利用には、細心の注意が必要です。個人的な利用にとどまる場合は問題になりにくいものの、SNSへの投稿や商業利用では、一般の著作物と同様に著作権侵害の可能性があります。
たとえば、AIが生成したイラストや文章を販売する場合、それが第三者の作品と酷似していたら著作権を侵害する恐れがあります。
特定できる音声である
著作権侵害の一例として挙げられるのが、生成した音声が、特定の人物だと簡単に判別できる場合です。現在の日本では、声に対する肖像権は認められていません。
しかし、音声そのものには著作権が認められています。そのため、声優の声を無断で録音してSNSに投稿したり、音声をコピーして配布したりする行為は、明確な著作権侵害です。
特定の声優や著名人の声を模倣したAIボイスチェンジャーが販売された事例では、声の著作権侵害に該当する可能性が指摘されています。生成AI技術を用いて音声を出力する場合は、元となる音声データの権利を確認し、必要に応じて許可を得ることが重要です。
以上のように、生成AIの進化は、音声著作物の分野にも影響を与えています。人間の声に近い自然な発音を再現できるAIが登場する一方で、声優やアナウンサーといった職業への影響が問題視されているのです。
ストーリーが似ている
動画生成AIも、著作権侵害と無関係ではありません。AIが生成した動画の内容が、既存の映画やドラマと酷似している場合、それがたとえ意図しなかった場合でも著作権侵害とみなされる可能性があります。
特にハリウッドでは、AIが脚本を代替する可能性が指摘され、これに反対するストライキが行われるなど世界的にも議論が続いています。動画配信サービスの一般化により、一般人でも手軽かつ簡単に動画投稿できる時代になりました。
しかし、動画生成AIで動画を生成して投稿した場合にストーリーなどが酷似していると著作権侵害に該当する可能性があるため、注意が必要です。
日本でのAI開発と著作権の現状
以上のように、日本の国内外において生成AIの活用が広がる一方で、著作権に関する課題が浮き彫りになっています。特に、生成AIがもつ法的リスクに対する懸念は、日本国内外で大きな議論を呼んでいます。
ここでは、日本でのAI開発における著作権の考え方について見ていきましょう。
著作権の基本
まず、著作権とは何なのか、基本を押さえましょう。第一に、単なるデータやどこにでもあるアイデアは著作物には該当しません。
また、著作物は、著作権者からの許諾を得なければ第三者は利用できず、許可を得ずに使用すると著作権侵害となります。さらに、私的利用や引用の場合など、特定のケースでは著作権の対象外となり、使用許可がなくても利用できます。
生成技術に関連する規定
著作物に表現された思想または感情の享受を目的としない利用は、著作権の対象外となり、許可がなくても使用できます。これは、AI技術の進展により新たに規定された新しい権利制限です。
言い換えると「生成サービスの利用者が既存作品に似せようという目的をもって生成しない場合に限り、著作権侵害が適用されない」ということです。しかし、既存の著作物を意図的に模倣する場合はもちろん、学習工程でデータとして取り込んでいた結果生成物が似通っている場合は、著作権を侵害していると判断されます。
AI学習自体は合法
現在の日本では、生成サービスに取り込む目的のみでの著作物利用は、著作権者の許可は必ずしも必要ありません。たとえば、インターネットに公開されているテキストや画像をソースとして収集・複製するのは合法とされています。
著作権侵害を問えるケース
著作権侵害の有無は、生成品と既存の著作物を比較し類似性があるか、依拠性があるかで判断されます。生成AIの場合、特に問題となるのが依拠性です。
生成AIは、与えられたプロンプトに対して統計的に最適な結果を生成する仕組みをもっています。しかし、その生成過程がブラックボックス化しており、どのようなデータや推論が用いられたかを事後的に検証することがむずかしいため、依拠性の有無が争点となりがちです。
判例などでは、利用者が生成元となった作品を認識しており、作風が残った生成物を使用した場合は依拠性があると判断され、著作権侵害が成立すると考えられています。よって、著作権者は、自身の著作物への接触や、自分の著作物に酷似していることを示すことで、著作権侵害と認定される可能性が高いのです。
また、著作物を認識していなかった場合でも、作品を学習ソースとして取り込んでいた場合は、類似した生成物に対して著作権を侵害している状態と判断されるケースもあります。一方で、他社の著作物を模倣しようとした認識がなく、さらに生成AIの開発・学習段階での学習がない場合は、類似した生成物は著作権を侵害していないとみなされる可能性が高いです。
リスク管理が重要
生成AIを安全に活用するためには、生成物が、学習段階と、生成および利用段階のどちらかに関連しているかを判断し、法的リスクを理解することが重要です。企業が開発・提供するサービスの学習段階では、何万もの膨大なデータが使用されます。
そのデータの中に著作物が含まれていた場合、生成物は権利侵害とみなされる可能性があります。一方で、技術的な仕組みによって、作風が生成物に反映されないように制御されている場合、依拠性がないとみなされる可能性もあります。
よって、企業が生成AIを利用してデザインやコンテンツを制作するときには、既存作品を学習データとして取り込んでいるか、著作物の特徴が生成されない仕組みをもっているか、慎重に確認しなければいけません。また、他社が開発したAIを使用する場合は、仕組みを理解し、法的に問題なく利用できるかを見極めましょう。
生成AI規制が進む可能性あり
現状、AI後進国ともいえる日本での、AI開発側に対する規制はそれほど厳しくなく、先進国でもっとも規制が緩い状態です。現在の日本の法律では、著作物をほとんど学習データ化できる状態であり、イラストレーターや音楽家、クリエイター側よりも優遇され、軋轢を生みかねない状態です。
しかし、このまま規制緩和された状態が永続するかといえば、その保証はありません。日本のAI開発は今後、法規制が強められる可能性が高いと考えられます。
そのままでは、外国の法律や規則に抵触し、安心してグローバルで商売できる状態にはありません。認識をブラッシュアップしないままの国外利用や、輸出をともなう場合には、そのデータの収集方法が問題視される可能性もあります。
場合によっては訴訟にいたるリスクもあるため、細心の注意が必要です。
まとめ
生成AIによる音声や画像生成には、著作権に対する懸念がつねに存在します。適切な許可なしにデータを収集した場合や、AIが生成した作品が既存の著作物に類似している場合、著作権侵害と判断されることがあります。音声においても、特定の人物と認められる声を生成し、商用とした場合、著作権侵害となる可能性があるため注意が必要です。生成AIは、クリエイティブ業界に革新をもたらす技術です。しかし、生成の際には生成物が既存の著作物に似ていないこと、学習モデルが著作物を学習していないことなど、法的リスクを理解することが大切になります。また、日本では今後、さらに生成AIに対する規制が強化される可能性が高いとされています。個人で判断するのが難しいと感じた場合は、AIの音声や画像生成が可能なサービスに委託し作成してもらうこともおすすめです。